

2000年の夏、
第一回ワークキャンプが行われた
“花の湿原霧多布”は、
出会える花々の数と同じくらい
あるいは更に多様な人々と出会える地でもあった
![]()
![]()

F.A.NのOBに長岡さんという方がいる。霧多布湿原センターのレンジャーであり、牡蠣のから剥き名人でもある。その彼が霧多布のレンジャーとなってから1年ほど経ったある日、F.A.Nにひとつの連絡をしてくれたのである。「霧多布でワークキャンプを受け入れたい!」
ちょうどその頃、F.A.Nではワークキャンプの更なる拡大を考えていた。そこにこの長岡さんの話が来たのだ。
しかもこの企画、F.A.Nの関係者が現地にいるというメリットもある。これを生かさないわけにはいかなかった。F.A.Nのことをよく知っている、しかもプロという立場の方に密接に関わってもらう中で、ワークキャンプとしてどういうことが出来るのかを新たに考えていく絶好のチャンスだったのである。
2000年から公式に始まった霧多布ワークキャンプ。だがその準備のために、1998年に一度、公募はせずに経験者の学生だけで試行ワークキャンプを行った。その中で、受け入れ先の霧多布湿原センターと霧多布湿原友の会の方々にも、F.A.Nとはやっていけそうだとの印象を与えることが出来たようだ。F.A.Nとしても霧多布での活動に魅力を感じ、長岡さんに間に立ってもらいながら本格的に準備を進めることになったのである。
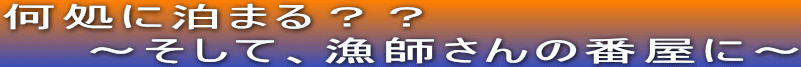
漁師さんの小屋である。 漁のできる期間に漁師さんが泊り込んだり、網や浮き、ロープにその他さまざまな漁の道具を閉まっておく場所でもある。 日常生活をおくる「家」とは別物なのだ。 |
![]() 1998年の試行ワークキャンプでは長岡さん宅に泊まらせてもらい、奥さんにもお世話になっていたが、ずっとそれを続けていくわけにもいかなかった。新たな宿泊先を確保しなければならなかったのだ。
1998年の試行ワークキャンプでは長岡さん宅に泊まらせてもらい、奥さんにもお世話になっていたが、ずっとそれを続けていくわけにもいかなかった。新たな宿泊先を確保しなければならなかったのだ。
そして、ワークキャンプを実施できるようになるまで約2年。どのような経緯で漁師である今さんの番屋に泊まれることになったのだろうか。ここはひとつ、長岡さんに語っていただこう。
サケの選別。雄と雌をその場で分けている。 |
「もともと、霧多布のある浜中町には、鮭鱒定置網漁の網元さん(多数の漁夫を雇用して漁業を営む人)が4人いたんですよ。 |
上の写真は番屋の中での宴会の一風景。 周りに置いてある漁具から、潮の香りが漂ってくる。今さんが炭火で焼いているのは牡蠣だ。 今さん自身はウェルダンのほうが気に入っているそうだ。 |
長岡さんは、少し息をついて再び語りはじめた。 「でも、漁師の雰囲気に満ちている今さんの番屋をそのままにしておくのはもったいない。そこで、私の勤めている湿原センターと友の会の今さんとの間で『漁師ミュージアム』を作ろうという構想が始まったんですね。 そこをどういう風に活用するか、については色々な案があるんですが、例えば『前庭ランチ』。欧米では、農家が自分のところで取れた食材を使ってランチを作り、一般の人相手に実施しているところもありましてね、その漁師版はどうか? と考えたんですよ。 他には、子どもたちの宿泊プログラムの拠点としてもいいですね。そういう話が出ているなかに私が、F.A.Nのワークキャンプの拠点として使わせてもらえないだろうか? ということを提案したんです。」 |
![]()


| 2000年、バードソンの募金先に新たに選ばれたのが霧多布湿原トラストだった。だが、正直、当時のF.A.Nの学生たちは霧多布についてよく知らなかったのである。 そこでGWに霧多布で、プレバードソンイヴェント・ネイチャーハントが行われることになったのだ。 そのときにF.A.Nとしては初めて、今さんの番屋を使わせていただいたのである。宿泊場所としては申し分のないところだった。 「ここはワークキャンプに使える!!」 今さんに打診したところ、今年の夏から使ってもかまわない、とのこと。早速、その年の夏、第一回霧多布ワークキャンプを実施することになった。 |
琵琶瀬展望台から霧多布湿原を見下ろす。 川が右手の海へと流れ込み、その河口を中心に人々は暮らす。古来より、ここは津波の多い地だ。 湿原のある内地に暮らすのは、その被害から逃れるためでもある。 |
初のワークキャンプ、ということで長岡さんに用意してもらった作業はフルコースだった。木道製作・設置、看板&標識製作・設置、ハスカップ移植、ほだ木(しいたけ栽培のための木)の運搬などなど。
セミナーも自然保護セミナー、チームワークセミナー、合意形成セミナー、バードソンセミナー、野外セミナーなど連日連夜目白押し。特に野外セミナーでは、1日で琵琶瀬展望台、湿原めぐり、ムツゴロウ王国(!?)、チーズ工場![]() 、小松牛乳工場
、小松牛乳工場![]() などを回った。
などを回った。
その上、地元の人からの歓迎会まで飛び入りであったのである。予定外に行われた地元の方主催のお茶会や、今さんの魚のさばき方講座などで午前中が埋まってしまったことも。おかげで非常に慌ただしくなったが、やはり嬉しかった。地元の方は、遠くからやってきた学生を歓迎ムードで迎えてくれたのだ。
だがもちろん、F.A.Nはお客さんではなくボランティアである。「ワークキャンプ」を継続していくためにも、そのことは受け入れ側の方々にも分かってもらわなければならないことだ。
|
その点は、当時のコーディネーターが特に気をつけていたことの一つである。 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
特に、「霧多布」という地域の自然保全活動の難しさとして、そこにいる人々の関係が特に複雑だということもある。それがまた、役場と市民と保全団体が協力し合おうとしている霧多布の魅力でもあるのだが、様々な立場の人がF.A.Nに関わってくれるのだ。
レンジャーとしての長岡さん、漁師であり子どもたちに文化を伝えていこうとしている今さん、東京から来て霧多布保全の土台を作り上げた伊東さん、トラスト活動を進める三膳さんをはじめとした理事の方々、役場の仕事で鳥獣保護も進めている久野さん…。他にも様々な人がいて、それぞれの関わり方をしている人たちと、F.A.Nがどう関係を作っていくのか?これからも考え続いていかなければならないだろう。
霧多布の長岡さんは、ワークキャンプを実施するうえで必要なことを3つ挙げてくれた。
![]() ひとつ目は、本当に自然保護につながる仕事(作業や調査)があるということ。
ひとつ目は、本当に自然保護につながる仕事(作業や調査)があるということ。
![]() ふたつ目は、受け入れ側の体制(宿泊先や受け皿)が整備されていること。
ふたつ目は、受け入れ側の体制(宿泊先や受け皿)が整備されていること。
![]() みっつ目は、現地にボランティアコーディネーターがいるということ(もちろん、場所によって、人によって差異はある)
みっつ目は、現地にボランティアコーディネーターがいるということ(もちろん、場所によって、人によって差異はある)
それらを維持するためにも、地元の方との人間関係、“つながり”を大切にしていかなければならないのだろう。その輪の中で、F.A.Nは活動していくのだ。
取材協力;長岡 滋雄、小日向 勇哉、掛下 尚一郎、松井 美奈(敬称略)
<赤瀬悠甫>